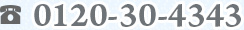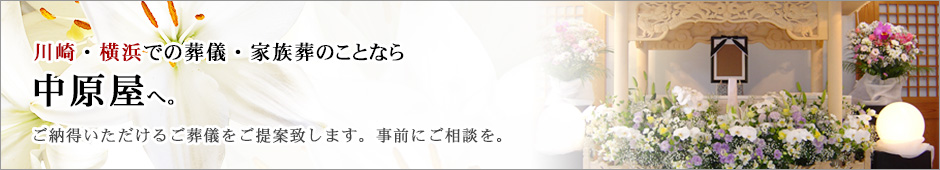実際の葬儀を担当している中原屋 原敏之が綴る、お葬式情報ブログ。
葬祭ディレクターとは
2013年12月25日 16:04
厚生労働省認定の「葬祭ディレクター技能審査」制度は、葬祭業界に働く人にとって必要な知識や技能のレベルを審査し、認定する制度です。葬祭業界に働く人々の、より一層の知識・技能の向上を図ることと併せて、社会的地位の向上を図ることを目的としています。
等級は1級と2級があり、1級は社葬や合同葬など大型葬儀を担当責任できる技量ということで、2級は通常の個人葬を仕切り担当責任できる技量ということです。知識と技量がないと現場で葬儀を執り行うなど怖くてできないと思います。
試験は、厚労省に届け出た規程に基づき葬祭ディレクター技能審査協会(平成7年設立)が実施しており、葬祭ディレクター(1級、2級)の認定は試験結果に基づき本協会が行っています。
私が取得したときは、学科試験と実技試験がありました。
学科試験は、結構細かいところまで出題されます。
実技試験は、司会や幕張りがあります。
幕張りは、すべて決まっている大きさで(ヒダの幅までも)30分間にバック幕、左右、シャンデリア2ツ、水引き、テーブル幕を1センチ以内の誤差で行うというものでした。
私は、京都の丁稚奉公でもかなりやっていたので、幕張りには自信がありました。京都では自宅葬が多かったので、天井まで幕を張る「天張り」までしっかりやるんです。先輩たちからは、手取り足取りなんて教えてもらえませんので、片付ける時に画びょうを一個一個取りながら覚えました。しかし厳しい先輩だと「幕張りなんかまだ早い」と、いっきに幕を引っ張って外してしまうんです(*_*; 磁石の画びょう取りがあり、それで画びょうをとりながら眺めていたりもしました(^^ゞ 余計な話でした・・・
さて、では資格を持っていたら信頼できるということでしょうか? ある程度の知識技量があるという目安にはなると思いますが、信頼できるできないというのは現場での経験から培われた「現場力」だと思います。現場では、確認と段取りが重要です。
あってはならないことですが、簡単な例を紹介しますと、通夜時に礼状と返礼品の確認をしていた際、字の間違いや品物の間違いがあったとします。すぐに修正や変更をしますが、通夜に間に合わないとなりません。よって万が一間違いがあっても修正や変更が可能な時間を予測して喪主に確認する必要があります。こういうことが「現場力」です。「間違ってました。すみません。」では、すみません。ほんとうに簡単な例えですが、そういうことの連続が現場なのです。